見附市学びの駅ふぁみりあでシリーズ開催されている「古代日本史講座」。
第16期の最終回となった本日は「平城京遷都と日本建国の謎を解く」シリーズの第4回目、近年日本各地で話題になることが多くなった「徐福」をきちんと史記から読み解いていき、さらに萬葉集に隠された「徐福」事跡を解き明かしていく。
「徐福」と聞いて、一般的には始皇帝に命じられて中国(秦)からどこかへ行った人というくらいの認識ではないか。日本各地には多くの徐福伝説が伝えられている。
関根先生は当初古事記の研究を始めたころに徐福に行き当たり、それ以降、古事記研究と共に徐福渡来の歴史的事実に興味を持っているという。しかし、一般的な徐福論と違うところがあり、本日の話はそのあたりを織り込んでいく予定。
■日本各地に伝わる徐福伝説
日本に伝わる徐福伝説は、例えば佐賀県関連では以下のような動画が作られている。
徐福伝説(佐賀県で明治生まれの人から聞き取り調査した内容を元にしている)
徐福ものがたり(佐賀市が作成)
また、鳥羽一郎が歌う「徐福男夢」という演歌も存在する。(この動画はカバー)
ネットで「徐福」を検索すると実にさまざまな情報がヒットする。近年、特に観光資源として徐福が取り上げられることも多くなっている。世界で一番大きい徐福像というものも見ることができる。また、神奈川県の海沿いの石垣で見つかった丸い石を徐福が渡ってきたときの船のウエイトと紹介しているものなどもある。
八丈島でも多数の丸い石が見つかっており、徐福の船団のものではないかと取り上げられている。もともと八丈島には江戸時代に滝沢馬琴が『椿説弓張月』という本を書き、源為朝が八丈島に流れ着いて、そこに暮らしていた女性と幸せになり、徐福伝説による祟りの恐れから男女別々の島に暮らしていたのを払しょくしたという話が知られるようになった土地でもある。
このように主に江戸時代あたりにヒットしたストーリーなどで民衆に広がっていった流れは大きいが、もう少し時代をさかのぼると仏教説話による伝承が広がっていったところもある。先ほどの佐賀の伝承は後者かもしれない。
■古事記と徐福
【資料1】古事記を学ぶ
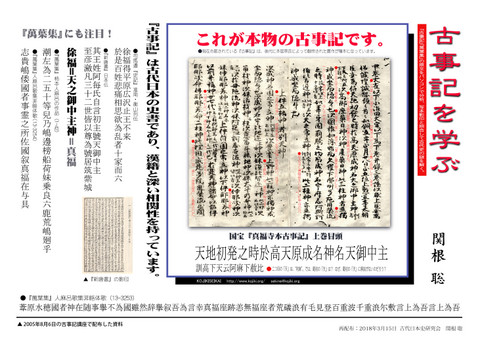
この資料右半分の写真は真福寺本古事記の冒頭部分。
本文は3行目5文字目の「天地初發~」からである。そして真ん中辺に少し大きめな字体で上下を空けて「上件五柱神者別天神」と書かれているのが目を引く。古事記の中でこのような書き方をしているのはこの部分以外にはなく、特別なところと考えられる。
「上件五柱神者別天神」
この記述だが、「この5人の神様は別な天の神である」と読める。本文先頭の「天地」とは日本地域のことと考えられる(日本の古い物語を神話という形で古事記は語っていると解するため)ので、別な神とは日本以外のところから来た神様ということではないか。
そして5人の神の短い説明にあるように、独り身で妻を持たず、逃亡者だったと感じる。
そう感じるのはそのイメージに徐福が重なったから。
それで作者は「徐福」を「天之御中主神」と書いたのではないか。秦から来た徐福は「真福」と書かれたようだ。真福寺は徐福を顕彰するために古事記を伝えてきたと考えている。
それを裏付けるものとして萬葉集の柿本人麻呂の作品(1-42)などがあるが、後程詳しく見てみたい。
しかし、これは直感的なものなので、まずは客観的にどうとらえるのかを考えなくてはいけない。そのためには初めて徐福を描いた司馬遷の「史記」にあたる必要がある。
■史記
司馬遷が2000年ほど前に書いたのが「史記」という本。手元には中国(台湾)で発刊された史記の影印と日本で木版本として発刊されたいわゆる和刻版の影印があり、徐福に関する記述の部分を比べてみると、若干違いがあるのが興味深い。
■じょふつ
史記に登場する徐福(じょふく)の名称は徐市(じょふつ)。(「徐」の国の「市」さん、という意味)
この「市」(ふつ)は和刻版では「市」(いち、し)の字で書かれているが、これは誤りで、「市」(ふつ)であることが重要である。
【資料2】『史記』に始まる歴史記述から数多くの「徐福伝説」が創作された。

この年表は徐福についての記述を辿って行ったもので、逵志保さんが作成されたもの。古来よりさまざまな人たちによって取り上げられてきたが、その変遷を概観することができる資料。「史記」によってはじめて「徐市」として取り上げられてから現在では「徐福」として研究テーマの一つを占めている。
大まかに分けて、まずは歴史上の実在人物として史記や漢書を研究していくアプローチがまずある。もう一つは各地に伝わっている伝説の中に史実を求めて調査するアプローチがある。また書誌学的にやったり民俗学的にやったり、研究課題はいろいろある。
最近目立つのは地域や先祖の事績を研究する活動で、それはよいことだが、自己満足に陥ったり観光目的のために徐福を利用する方向に走ったりするのが気になる。
■徐福研究文献1
【資料3】資料紹介 逵志保『徐福伝説考』(一季出版1991)

徐福に関してしっかりとした研究を初めて行ったのがこの逵志保(つじしほ)さんではないか。1991年に発行されたこの本、元は大学の卒業論文だが、わかりやすく評価も高い。実際に読むと面白い。著者が女性ということもあり徐福界のマドンナ的存在になっている。
資料で紹介しているのは「徐福伝説のいきさつ」と題された部分。中国で最初に徐福が描かれるのは漢の時代、司馬遷の史記からであること。名前は徐市(じょふつ)であり、童男女数千人をつれて渡海したが失敗して9年後に戻ってくるという内容が紹介されている。
これが徐福伝説のもとになる記述であるとしている。
歴史的事実として受け入れるべきこのことを元にしている内容からも、しっかりした本であると評価する。徐福に関する書籍は手元にあるだけで40冊ほどにもなるが、この逵さんの本は一番しっかりしていると思う。
逵さんはこの後、大学院での修士論文を元に「徐福論」という本も出しており、内容は非常に充実している。
現在、各地各方面から引っ張りだこということもあり、それぞれの地方、分野の徐福の扱いを受け入れるた立場をとっている。懸念としては、史記、漢書そしてそこから出てくる徐福の本当の像についての踏み込みが足りない感がある。現在は再販されていなく、中古市場ではプレミアがついている。
■徐福研究文献2
【資料4】資料紹介 いき一郎 『徐福集団渡来と古代日本』(三一書房1996)

著者はジャーナリストであり、極力客観的にものを書こうという立場が貫かれてかなり面白い本である。
資料に紹介したのは史記列伝に記載されている伍被という将軍の話。秦の時代の三大悪人の一人として徐福をあげている。
一つのポイントは本紀では「徐市」(じょふつ)として登場していたが、列伝では「徐福」(じょふく)となっているということ。
もう一つのポイントは、「東渡集団」という言葉でとらえ、無事到着し王になったと伍被が言っているということ。
さらに著者は「童男女は始皇帝に滅ぼされた六国の子女だったと考えられる」と書いており、これは非常に洞察に富んでいると考える。いわば貢物として連れて行った童男女であり、秦本国の人民でなく敗れた国々から集めたと考える方が筋が通る。
ただし、東渡した人数が童男女に水夫等を加え一万人以上という推定には賛成しかねる。史記で三千人、漢書で五百人と書いており、敗れた六国それぞれから五百人集めたとすると三千人となり、理にかなう。その内、童男を水夫として訓練したのではないか。
■徐福研究文献3
徐福論を語るにはまずは史記をちゃんと読むことが最も重要である。そういう意味で数ある徐福文献の中でちゃんと読んだと思えるのは先にあげる2人しか見当たらず、多くの本は史記の一部を取り出して論じているにすぎない。まったく史記の記述に触れない本もある。
しかし、漢文で書いてる史記を自分で読むのはものすごくハードルが高い。そこで、自分はまず筑摩書房の「世界文学大系」に掲載されている史記の和訳を読んだ。さっと目を通す読み方に最適。例えば、秦の始皇帝は残虐というイメージがあるが、滅ぼした国のいいところを取り入れて、それをちゃんと行えるものはトップに据えて運営したから統一ができた、というようなことも書かれている。自分の目で原典を読んでみるというのは大切であり、この和訳は読みやすくとてもよいと思う。
【資料5】資料紹介 新釈漢文大系92 『史記12列伝五』(明治書院2007)

こちらは研究・分析・調査に適している。原文、訳文、通釈、語釈が並べて書いてあり、客観的に把握できる。
資料に紹介しているのは先ほどのいき一郎さんが取り上げていた伍被の話の部分。
まず、本紀では「徐市」(じょふつ)と書いている人物が、列伝では「徐福」という書き方に変わっていることが興味深い。「市」と「福」は中国語では同じ発音ということだが、悪人として登場した際に、より好ましい字である「福」になっているのはなぜだろうか。
■百越と李斯
もうひとつは、「尉佗」についての記述部分。尉佗は始皇帝の死に乗じて、赴任先の楚地域を簒奪(さんだつ)し、南越国の王を称した。さらに衣服を繕わせるために3万人の未亡人を秦に要求。秦の皇帝は1万五千人を供出することを認めたと書かれている。
どうして司馬遷はこんなエピソードを史記に収録したのだろうか。
百越という国をキーワードに面白い推論ができる。
楚が滅びる60年くらい前、楚は百越を併合している。始皇帝に仕えた宰相に有名な李斯(りし)がいる。李斯は始皇帝の腹心であり、李斯という人なしに始皇帝が何かをするということはまずなかったと思われる。蒙恬にしても尉佗にしても徐福にしても李斯によって動いたのではないか。李斯は楚の出身で地域ははっきりしていないが百越にからんでいた人なのではないかと推定している。
さらに、尉佗が管轄した楚には大型船を造る技術があった。徐福船団の船を作ったのは尉佗ではないのかという結論に至る。
■李斯のもくろみ
さらに推論を進めると、徐福を派遣したのは始皇帝と言われているが、実は李斯ではなかったのかと考えられる。
始皇帝は六国を平定してひとつの統一国家を作るわけだが、それに一番貢献したのは李斯。しかし、李斯の立場からするともともと敵国の人物なので、国が全部まとまったときに一番煙たがられるのは自分ではないかということを恐れていた。参謀というのは一番たよりになると同時に一番怖い存在でもあった。
それで、李斯が自分の逃げ場所を東西に作ったのではないかと推定する。ひとつは海を渡ったどこか、もう一つは自分が生まれ育った場所である。前者は徐福に、後者は尉佗に託したのではないか。徐福東渡の裏にはそんな事情があったと考える。
■百越の女の子たちと日本
三千人の子供たちを連れていくときにどうやって統治すればいいか。第一に共通した言葉が必要だろう。
女の子千五百人を全員百越の女の子に交換してしまうというのがいい方法と考えられる。女の子同士は百越の言葉を共通の言葉として話せるが男の子同士は話せない状態になる。そういうことができないかと巡らせているときに百越で船を作っている尉佗が出てくる。百越の女の子千五百人(あるいは千二百五十人)を教育係兼世話役として登用、東渡時に交換してしまったのではないか。
それを命じたのは李斯。始皇帝が亡くなって権力争いに敗れるのだが、その手前のところで尉佗の事件が起きた。尉佗は千五百人の女の子を交換したことを使っておどしをかけた。三千人の10倍の三万人をよこせと言ったが、お前が手配したのは千五百人の女の子だけじゃないか、その10倍の一万五千人で十分だ、というような対応を李斯が行ったと考える。その記録がこれではないかと感じている。
なぜそういう推察をするかというと、東渡した女性がすべて同じ国(百越)の人であれば結果的に女優位になる。楚の男の子と楚の女の子のグループは楚の純粋種であり、日本の天皇家のもとになっているのではないか。そういう人がまずあって、その他は混血ということになる。しかしみんな百越の血を引いている。そして日本のどこかには楚の男の子と女の子の集団がいて、天皇家のもととなる場所があった。かつ日本各地に混血のところがあった。という地域が少なくとも6つくらいはあったと思われる。
そのうちの一つがたぶん新潟だったのはないか。それを直感的に感じているのが邪馬台国新潟説を唱えている桐生さんという方で、ある種当たっていると思う。百越というところをとらえているのはしかりだなと思う。また、「越」という部分が大きなポイントである。
冒頭の佐賀県の民話の中にも魚の話で「えつ」という言葉が出てきた。
司馬遷は、編纂途中で徐福東渡の歴史的事実に気づいたのだ。しかし、本紀と列伝記述作の間に、李陵の弁護がもとで自分が腐刑されるという難にあっている。司馬遷は、徐福東渡の事実を直接書くことを避け、伝文の形をとりオブラートに包んで書き表した。
■古代史をイメージし、邪馬台国を探る
古代史は、ある種の資料が出てきたものをどう自分が想像して補っていくかということが結構ある。それは各人に許されている。というか、しなければ繋がっていかない。しかし、できるだけ客観的な論理が裏付けとして必要だ。
そう考えると邪馬台国の話も少し見えてくる。なんで国がばらばらになって、それをまとめるのが卑弥呼という女王だったのか。卑弥呼は実在したと思われ、今ほどの主張からすればそうなる可能性が非常に高いと考える。女性がつながなくてはならない歴史的背景があった。
なぜ30か国に分かれて戦乱状態になったか?
「独身で隠身の5人の神々がいた」と特別に表記されている古事記には「くにわかくして、くらげのごとくただよえるとき」と書かれ、楚の男の子と楚の女の子がいた地域、つまり徐福集団中心グループがいて一番繁栄して、2000年前に大災害があって、すべて流されてしまった。
それが関東地方であることは、実際に住んでみるといい場所であることからも想像される。ところが関東地方南部には縄文遺跡はたくさんあるのに弥生遺跡がほとんどない。海抜10m以下は皆無と言っていい。千葉県西海岸部には数千の貝塚があるが、人が住んでいた遺跡は何もない。住居遺跡はなく貝塚だけがたくさんあるというのは、この頃に大災害があったとしか思えない。
7年前、東日本大震災の時の大津波被害を目の当たりにして、この思いを強くした。
天皇家の元というのは関東地方に住み着いた徐福集団の核だったが、大災害でその核がなくなりばらばらになった。その再編成が邪馬台国であると考える。
問題は、楚の童男女の子孫がほとんどが死滅、特に女性がいなくなった。それで残りの五国の中から女性を嫁がせるという形となる。大和地方には「大和六県」(やまとのろくのあがた)というのがあった。大和地方には特別な六の地域があり、それぞれの地域から天皇家に女性を差し出すというしくみが大和の初期段階にあったらしい。
次回シリーズの講座で日本書紀を詳しく取り上げるが、このあたりについても丁寧に解きほぐしていきたい。
■萬葉集から徐福を探る1【鹿】
資料4の下欄外に記載してあるキーワードで萬葉集を検索してみる。
萬葉集を「鹿」で検索すると、最初に柿本人麻呂の作品(1-42)がヒットする。
![]()
原文:潮左為二五十等兒乃嶋邊榜船荷妹乗良六鹿荒嶋廻乎
解釈してみる。
潮左:潮(うしお)が東(左は東の意)に行った→徐福集団の例えではないか
良六鹿荒嶋廻:優れた(良)6つの徐福集団(鹿)が未開地(荒嶋)を廻った
榜船荷妹乗:かい(榜)の船に妻(妹)を乗せて
二五十等兒:九九で二五十→とう。つまり「二五十等」で「とうと」→東渡した子供たち
日本語で「十」を「とう」または「と」と読む理由はこの作品から来る概念と考える。「二五十」を「東渡(とう・と)」と読むことから始まったのではないか。以前取り上げた「おみなえし」に見えるように、萬葉集は日本語づくりの記録であったと思う。
■萬葉集から徐福を探る2【鹿子】
今度は「鹿子」で検索してみる。
![]()
原文:名兒乃海乎朝榜来者海中尓鹿子曽鳴成・怜其水手
訓読:名児の海を朝漕ぎ来れば海中に鹿子そ鳴くなるあはれその鹿子
末尾の「鹿子」の訓読を見てもわかるように「水夫」のこと。つまり人麻呂の歌で見たように「六鹿」は徐福の6つの集団を表し、さらにこの歌で見るようにそれぞれの集団(鹿)の童男たちは水夫であったということ。先ほど徐福集団の童男を水夫として教育したという話をしたが、その証明となる歌である。
■萬葉集から徐福を探る3【さ雄鹿】
![]()
原文:竿志鹿之心相念秋芽子之鐘礼零丹落僧惜毛
「さ雄鹿」は「竿志鹿」表記されている。舟をこぐ「竿」であり、ここでも「鹿」にからむと船がらみの言葉であることがわかる。ほかの歌では「さ」を「小」と書いている歌もあり、子供たちのことを表していると考えられる。
また「左男鹿」表記(6/1050)から、彼らが「東男」になったことが推察できる。
さらに「狭男壮鹿」(5/1047)という表現も、埼玉県には「狭山」という地名がある。交通の要所で、やや高台。大災害の難を逃れた童男の子孫がいた地域かもしれない。戦前には陸軍航空士官学校(現入間基地)があった。
ちなみに、萬葉集冒頭の作品には大和の国が「山跡乃國」(1/1)と記されている。
萬葉集で「鹿」を追っていくと船に関すること、しかも人を含んだ意味の使い方が定着していると言える。
■まそ鏡と徐福
【資料6】萬葉集「まそ鏡」用例と古代日本の歴史的事実

資料に掲載しているように萬葉集で「まそ鏡」用例は35回。
「喚犬追馬鏡」という表記では犬を呼び寄せるのに「マ」、馬を追うのに「ソ」と言ったという学説がある。これはとんでもない誤りだ。
本来「追馬」とは競馬用語で馬に鞭を入れて強く走らせること。
それで、「犬を呼び、馬を走らせる」絵柄の鏡を探していると、数年前ヤフオクに出品された!! その時は落札できなかったが、昨年末にまた発見し、今回は落札できた。レプリカだと思うが、解説には8世紀の唐の品とあった。実際に入手したものの写真を資料に載せているが、実物を本日持ってきているので見てほしい。
資料に載せた「まそ鏡」の用例は様々な表記がある。本来の意味となるのは「真十鏡」であり、15回の用例がある。
「真」を「秦」の国、「十」を徐福の史記で登場した時の名前「徐市」の「市」の構成文字である「十」と解すると「秦からやってきた徐福」ととらえられる。
「徐市」の「市」は「十」+「冂」(けい)に分けることができる。「冂」という字は邑(=みやこ)の外の郊、郊の外の野、野の外の林、林の外が冂、ということでとんでもなく遠いところを意味する。司馬遷が「徐市」と記したのは「とんでもなく遠くへ行った十さん」ということではなかったか。そんなところからも徐福と萬葉集とつながってくる。
■日本書紀に隠された意味
資料の右下に《参照》として示してある2つの言葉は、まそ鏡の延長で発見した、日本書紀に登場する興味深い表記である。
一つ目は、国生みの最初に出てくる「オノゴロ島」の読みで知られる島の名前。
先頭の字は「石」と「殷」が一緒になった字であり、「殷」は古代中国の名前であると同時に「立派な」という意味を持っている。(資料に記してある数字は「漢字海」(初版)の掲載ページなので、自分で調べてみてほしい)
2文字目の「馭」は「統率する」、3文字目の「慮」は「おもんばかる」という意味であることがわかる。
つまり「立派な石さんが統率しおもんばかる島」ということになる。→「石さん」はもちろん石上麻呂を指す。
二つ目は「日本」という言葉に対する訓注表記で登場する。
「耶」は父を呼ぶ言葉。「騰」は馬に乗る。→「麻とうちゃんが馬に乗る」→「麻とうちゃん」はもちろん石上麻呂を指す。
石上麻呂の初見は『日本書紀』天武元年(672)七月壬子(7月23日)の条にある。「物部連麻呂」の名で登場し、大友皇子の自死を看取っている。大臣・諸将が四散して逃げる中、麻呂はただ一人、大友皇子を最後まで護衛した”騎士”だった。その後、大乙上(上から数えて19番目)という低い階位から身を立て、臣下の最高位・左大臣(708)となる。
『日本書紀』でオノゴロ島が「磤馭慮嶋」、日本が「耶麻騰」と、「石」「麻」「馬」がらみで表記される理由を考えたい。
つまり、日本の事始めと日本の読みを石上麻呂で表しており、日本書紀の作者は面白いことをしている。この辺の紹介は次回の日本書紀シリーズでもっとご紹介できると思う。

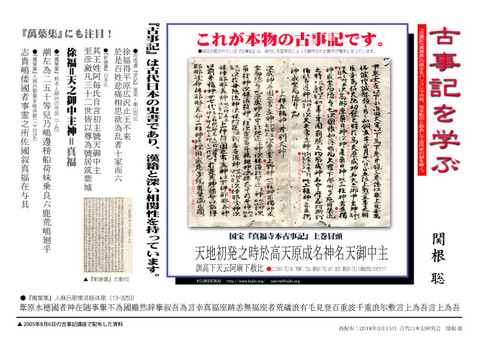
コメント